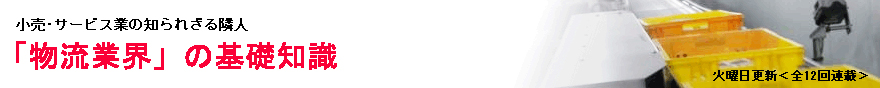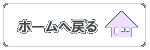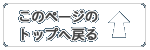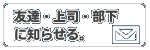vol. 12 荷役を担う港湾運送やターミナル業界
★輸送の中継点に必要となる荷役の作業
船舶や航空機、鉄道といった輸送機関は、
国際間も含めた広域の輸送に使われるため、
発着荷主のいる都市と最寄りの鉄道駅や港湾、空港間の輸送のために、
他の輸送機関に荷物を積み替えることになる。
また、発荷主から着荷主まで
“ドア・ツー・ドア”の輸送が可能だといわれる自動車輸送でも、
一部の荷物を除いて、実際に同じトラックで全区間を運ぶわけではない。
通常は、コストも含めた輸送効率の面などから、
都市内の集荷配送は中小型トラック、
都市間の幹線輸送は大型のトラックというふうに使い分けられている。
そこで、輸送機関やトラックを変更し、
集めてきた荷物を方面別にまとめたり、
逆に大量に混載された荷物を仕分けしたりするために、
いったん積み降ろしたり、倉庫に保管するための荷役の作業が必要となる。
このような荷役の作業を担い、
輸送の中継点としての役割を果たしているのが、
駅や港湾、空港に設けられた物流ターミナルである。
荷役は輸送や保管と不可分の面があるため、
人類がモノを運ぶようになった時点から存在し、その歴史は古い。
モノが集散する宿場や港には、古くから荷役を行う人たちが必ず控えており、
その中から港湾運送事業者が生まれた。
陸上の物流が鉄道主体になると、
各駅で荷物を扱う通運会社(フォワーダーの前身)が誕生。
やがて、陸運の中心が自動車に移ると、
都市近郊の高速道路やバイパス沿いにトラックターミナルがつくられ、
陸運の中継点としての役割を果たすようになった。
現在、港湾運送事業者の数は940者弱(2006年度)。
地域性が強く、それぞれが地元の港湾を主体に事業を行っていて
各事業規模はあまり大きくないが、
事業者の営業収入を合計すると1兆円超となる
(2005年度、いずれも国交省調べ)。
一般トラックターミナルについては、
全国に17事業者、23か所(2006年度、国交省調べ)ある。
公共性も高いため官主導でつくられてきた経緯もあり、
自治体と民間の共同出資による第三セクターが多い。
空運の荷役については、輸送機関が飛行機ということで、
荷物自体の大きさや重量が限られているため、
航空機会社やフォワーダーなどが担うことが多く、
専門の荷役事業者が占める割合はあまり大きくない。
さて、小売業・サービス業の商品や原材料の供給などを
裏方として支える物流業界について、
12のテーマに分け14回にわたって紹介してきた。
拙い連載が、「知られざる」パートナーの理解に、
少しでも役立てていただけると幸いです。
最後になりましたが、この場を提供してくださった商人舎さんと、
読者の皆さんに心から感謝申し上げます。
(完)
〈by 二宮 護〉